B型肝炎とは
B型肝炎ウイルス(別名:HBV)が人の血液や体液を介して発症する肝臓の病気です。
現代では多くが母子感染、または成人以降は性行為の際に感染するため、性病の一つに分類されます。
一過性感染と持続感染の違い
感染した際の環境や遺伝子タイプによって、「一過性感染」と「持続感染」と異なってきます。
一過性感染
B型肝炎ウイルスが体内に入り、1ヶ月から半年間の一時的な感染のことを指します。
成人してから私たちの免疫機能によって、通常は一時的なものでウイルスが体外に排出され、自然治癒することが一般的です。
性交渉が経路となる場合、「性病」としてB型肝炎に感染するのは、一過性感染が大半を占めています。
持続感染
B型肝炎ウイルスに感染してから半年以上にわたってその感染状態が続くことを指します。持続感染した場合、その方々はB型肝炎キャリア(HBVキャリア)と呼ばれます。
免疫が確立されていない幼少期または出産時の母体を通じて感染した際には、ウイルスを体外に排出できず、高確率で持続感染となります。
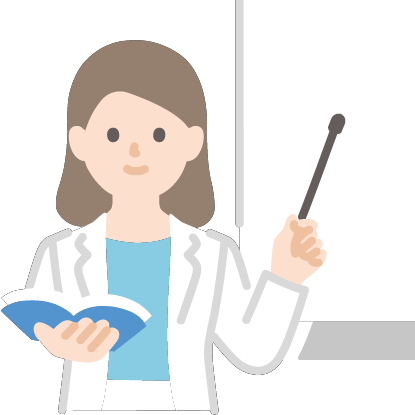
成人してから初めて感染しても、”ジェノタイプA”というタイプのウイルスであれば、10~15%程度の確率で持続感染となることがあるため注意が必要です。
B型肝炎の症状
B型肝炎の症状ははっきりあらわれる方とそうでない方と個人差もあります。 主な症状はどれも男女ともに同様です。
| 慢性肝炎 | 急性肝炎 | |
|---|---|---|
| 感染状態 |
持続感染
またはジェノタイプAのHBV感染 |
一過性感染 |
| 潜伏期間 | 半年以上~数十年間感染が継続する | 1ヶ月~半年ほど |
| 症状があらわれると |
・食慾不振
・倦怠感 ・尿の色が変わる(黒褐色) ・黄疸 など |
・倦怠感
・熱 ・吐き気、嘔吐 ・尿の色が変わる(黒褐色) ・黄疸 など |
| 感染経過 |
1. 数年~数十年間は肝炎を発症せず【無症候性キャリア】
2. 思春期を過ぎたあたりで肝炎を発症 →徐々にウイルス減少、非活動キャリアに |
・症状があらわれず自然治癒
もしくは、 ・上記症状があらわれてから数週間で回復・自然治癒 |
| 重症化した場合 | 肝硬変が起き、さらに悪化すると肝がん |
劇症肝炎
→死亡率が高くなる |
B型肝炎の感染原因
感染した経路によって「垂直感染」か「水平感染」か異なります。

|
|
| 垂直感染 | • 出生時の母子感染 |
|---|---|
| 水平感染 |
• 傷のある皮膚への体液の付着
• 濃密な接触(性行為など) • 静注用麻薬の乱用 • 刺青 • ピアスの穴あけ • 不衛生な器具による医療行為 • 出血を伴うような民間療法 • その他 |

|
|
輸血・注射によるB型肝炎感染
- 以前までは輸血による感染もありましたが、1972年から輸血に際した抗原検査が導入されて以来、B型肝炎感染者数は減少し、輸血での危険性はほとんどありません。
- また注射針の使いまわしが昭和63年まで行われていましたが、現在では医療現場における徹底した再使用の禁止により、危険性が大幅に減少しました。
成人の感染原因は性交渉が多数
- 成人における急性B型肝炎の多くは、性感染によるものとされています。
- 感染経路はHIVと同様ですが、B型肝炎ウイルスは感染力が50倍から100倍も強力です。さらにヒトの体の外でも生存でき、最低でも7日間は活性状態にあります。
B型肝炎の治療法
性感染などのB型急性肝炎の場合、自然治癒することも少なくありません。
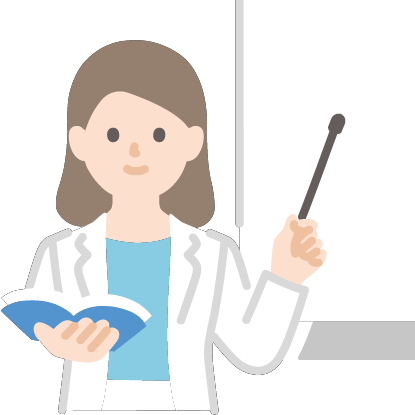
症状が重度ではない場合、抗ウイルス薬などは用いず安静にして様子を見ます。
症状が重い場合やウイルスが排除されない場合は、抗ウイルス療法または肝庇護療法が行われます。
劇症の場合は、肝移植が最も生存率の高い効果のある方法とされています。
抗ウイルス療法について
抗ウイルス療法は、インターフェロンや核酸アナログ製剤といった薬物が用いられます。
肝庇護療法は直接ウイルスに対して作用するものではなく、肝細胞の破壊を抑制し、肝機能を改善・進行を遅らせることを目的にした治療方法となります。
B型肝炎の感染予防・対策
B型肝炎は通常以下のような、日常生活の行動では感染しません。
- くしゃみ、咳
- 蚊
- トイレ、入浴
- 握手、ハグ
- 汗、尿、涙などの体液以外の分泌物
血液・粘膜との接触に気を付ける
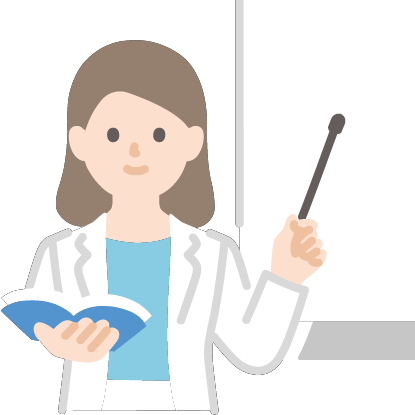
普段の生活では、血液や粘膜は触れてしまうタイミングに気を付けましょう。
B型肝炎の感染リスクを避けるために気を付けるべき行動はこちらになります。
| 生活習慣内 |
・粘膜、血液が付く可能性があるものを他人と共有しない(タオル、カミソリ、歯ブラシなど)
・鼻血や切り傷などの出血はできるだけ本人以外が素手で触らない |
|---|---|
| 性交渉 | ・性交の際にはコンドームを正しく使用する |
| その他 |
・ピアスを開ける際は不衛生な器具は使用しない、使いまわししない
・できるだけ入れ墨やタトゥーは行わない |
事前予防・ワクチン接種
B型肝炎の予防にはワクチン接種が非常に効果的で感染リスクを最大限減らすことができます。
WHOは成人でのワクチン接種を以下の方々に推奨しています。
- 医療関係者
- 医療従事者以外で血液、血液製剤にさらされる可能性のある方
- 性交渉をする相手が複数いる方(風俗店などで働いている方など)
- 透析患者や臓器移植を受けた方
- 頻繁に輸血などを必要とする方
- B型肝炎の感染者とパートナーの方
2016年以降、B型肝炎のワクチンが定期予防接種の対象となりました。
そのため国内では現在、生まれたばかりの乳児に適用され、抗体が陽性になることでB型肝炎に感染リスクが極めて低くなります。
B型肝炎の再発について
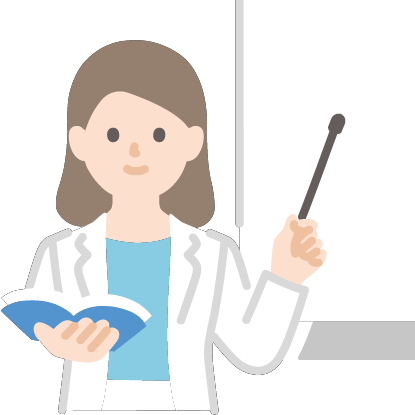
B型肝炎が治癒した後、抗体ができるため健康な状態であれば再び発症することはありません。しかし、重い病気になり、免疫抑制の状態になるとウイルスが再活性化し始めてしまうのです!
B型肝炎ウイルスの再活性化
知っておくべき点としては、近年の研究では一過性感染が治癒したとしても微量のウイルスが残留することが分かっています。
これらが免疫治療・化学療法(抗がん剤等)などを受けた際に再活性化する可能性があります。
再活性化し、発症したB型肝炎は重症・劇症化率が高く、そうなってしまった場合、免疫療法など別の治療が行えなくなる危険性も出てきます。
B型肝炎を放置すると
B型肝炎を放置すると、自然治癒する場合と重症化またはキャリア化する場合があります。
急性B型肝炎は自然治癒する?
一般的に、成人が初めてB型肝炎に感染した場合、ほとんどの方は”一過性感染”となります。
無症状のまま自然治癒(70%~80%)
成人してからB型肝炎ウイルスに感染すると、70%~80%の方が発症せず(無症状)、ウイルスが体内から無くなり自然治癒します。
発症しても自然治癒が大半(90%)
上記の無症状以外で約20%~30%の方が急性B型肝炎を発症することがあります。 多くの場合は2,3か月経過すると、ウイルスが排除されて自然治癒します。
稀に劇症肝炎に(1~2%)
急性B型肝炎を発症した中で、稀に劇症肝炎と呼ばれる症状を引き起こす可能性が1~2%ほどあります。 劇症肝炎は急激に高度の肝機能不全を引き起こし、高い確率で死亡に至る危険性があります。
B型肝炎に関するよくある質問

B型肝炎はキスでうつりますか?
感染する可能性はゼロではありません。
粘膜や体液が感染経路のため、B型肝炎を発症している、また危険性があるタイミングでのキスや性交渉は避けることが予防となります。

B型肝炎は他の性病より感染力が強いですか?
一般的にHIVやC型肝炎と比較して感染力が高いとされています。
感染経路は同じですが、B型肝炎ウイルスは体内に最低でも7日間生存できる特徴があります。

B型肝炎の検査はいつからできますか?
B型肝炎は感染機会から2ヶ月以上経過していないと血液中で判断ができません。
正しい結果を得るには、基本的には2ヶ月以上空けて検査をしましょう。

B型肝炎ワクチン接種後であれば、性交渉しても感染しませんか?
感染する可能性はあります。
B型肝炎ワクチンにて抗体が得られれば、高い確率で感染を防ぐことができる有効な手段ですが、体質により抗体が作れらなかった場合は、性交渉をすれば感染するリスクがある事を知っておきましょう。

B型肝炎が陽性だった場合の治療は何がありますか?
急性B型肝炎であれば、多くの方が無症状もしくは症状があらわれたとしても、自然治癒することが大半です。
そのため一般的に薬などを用いた治療が必要ないとされています。
劇症の場合は、抗ウイルス薬または肝移植の治療法が用いられます。

大人になってからB型肝炎に感染し、治ってからはもう二度と感染しないのでしょうか?
成人での一過性感染の場合、治癒した後は健康な状態であれば再発はほとんどありません。
ですが、近年治癒しても体内からB型肝炎ウイルスが完全に除去されるわけではないことが分かってきました。
そのため、抗がん剤治療など免疫が著しく低下する状態になれば、B型肝炎ウイルスの再活性化によって重度の肝炎を発症する可能性があります。